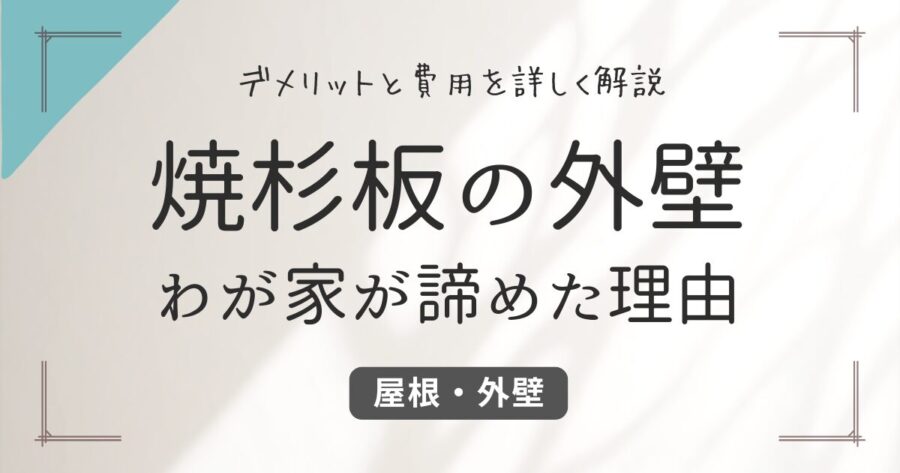住宅の焼杉板外壁に憧れを持つ方は多いのではないでしょうか。岡山県では昔から焼杉板を使用した住宅が多く、その独特の風合いと機能性から近年再び注目を集めています。
わが家も新築時に焼杉板外壁を強く希望していましたが、最終的に採用を断念することになりました。
この記事では
- 焼杉板外壁の費用相場、メリット・デメリット
- 採用を諦めた具体的な理由
これらのことを実体験を交えて詳しく解説します。
また、代替案として採用した焼杉板風サイディングの使用感もレビューしますので、外壁材選びの参考にしてください。
焼杉板外壁とは?基本的な特徴
焼杉板は、杉板の表面を焼いて炭化層を作った外壁材です。日本の伝統的な建築技術で、特に瀬戸内地方で多く使用されてきました。
焼杉板外壁の製造方法
- 三角焼き:杉板を三角に組んでじっくり焼く方法(推奨)
- バーナー焼き:バーナーで表面を焼く方法(耐久性に問題あり)
焼杉板外壁の3つの主要メリット
焼杉板のメリットとして注目したいのが以下の3点。
- ランニングコスト
- 経年変化
- 熱伝導率が低い
他にも防虫、防腐、防火の効果もあります。
優れたランニングコスト(長期的なコスパ)
外壁を選ぶうえで検討するのが導入時にかかるイニシャルコストと、導入後のランニングコスト。
上手に選ぶためには50年先を見据えて、どれが一番コストパフォーマンスが高いかを見極める必要があります。
今回は塗膜保証が30年の窯業系サイディングで高耐久シーリングを使用した場合と焼杉板で比較します。
| 外壁材 | 新築時費用 | メンテナンス費(30年後) | 50年総コスト |
| 焼杉板 | 280万円 | 0円 | 280万~ |
| 窯業系サイディング | 150万~180万円 | 180万~200万円 | 330万~380万円 |
窯業系サイディングでも最近は高耐久のものが出ていて、シーリングも高耐久のものにすることで30年間ノーメンテも実現できるみたいです。比較表のメンテナンス費で新築時より値段を上げているのは、物価上昇を織り込んでいるからです。
焼杉板外壁は基本的にメンテナンスフリーと言われているので、初期費用が掛かっても50年で見ると強いです。
味わい深い経年変化
焼杉板は時間の経過とともに炭化層が自然に剥がれ、独特の風合いを醸し出します。この経年変化は人工的に作り出せない本物の木材ならではの魅力です。

写真は築50年ほど経過した焼杉板外壁です。炭化層がかなり剥がれてきてはいますが、見た目だけのことをいうと十分カッコいいです。
優秀な断熱性能(熱伝導率が低さ)
木材は多くの隙間を持つため、熱が伝わりにくい断熱材のような構造をしています。
| 材料 | 熱伝導率λ[W/m・K] |
|---|---|
| スギ | 0.097 |
| 窯業系サイディング | 0.17 |
| 漆喰 | 0.727 |
| ステンレス 鋼 | 24.74 |
参照:建築材料・断熱材の熱定数(熱伝導率・容積比熱)まとめ | 建築学科のための環境工学
この低い熱伝導率により、黒い外壁でも表面温度の上昇を抑制でき、室内環境への影響を最小限に抑えられます。
これだけのメリットを持つ焼杉板なので、絶対に採用したかったのですが、やはり費用の壁が立ちはだかりました。
焼杉板外壁を諦めた理由|費用面での課題
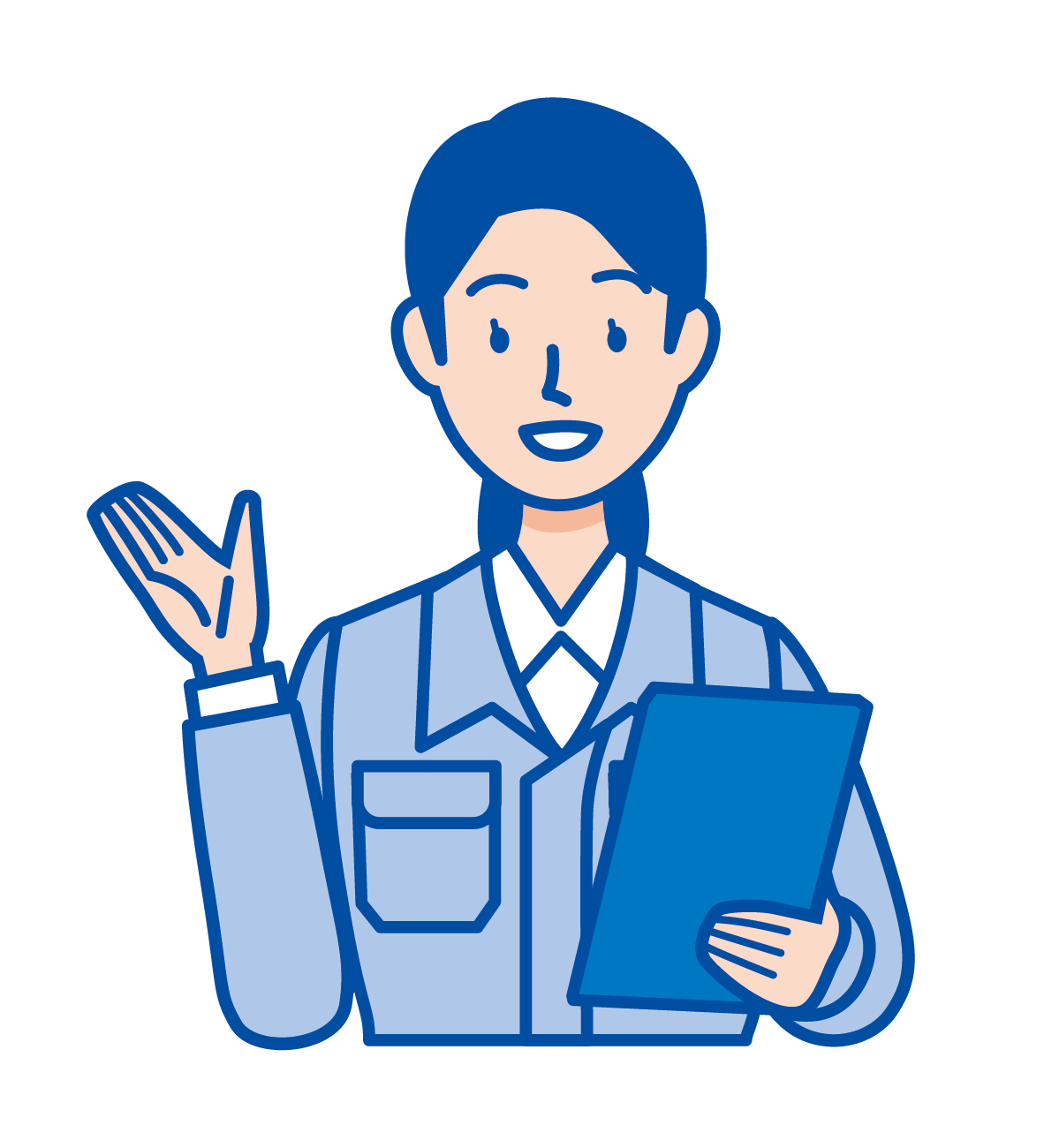 工務店
工務店焼杉板外壁にするとプラスで120万円です。
た、たかい。。。
DIYで施工することも検討していたので、個別に価格を出してもらいましたが、
焼杉板の材料だけ→約30万円
焼杉板を張る人件費→約30万
残りは下地の費用でしたが、焼杉板含む木質系の外壁の場合はこの下地がネックになってきます。
省令準耐火構造で焼杉板外壁は費用増
わが家が契約した工務店は省令準耐火構造が標準仕様でした。
焼杉板は一般的な建材より防火性は高いものの、省令準耐火構造の基準を満たすには追加の下地工事が必要となります。それが60万。。。
工務店の方の説明ではモルタルを塗るか、ベースとなるサイディングを張った後に焼杉板を施工するという説明で、「言うなれば二重外壁なんです」ということでした。
コスト削減の代替案
最終的に、以下の方針に決定しました。
- 新築時:焼杉板風サイディングを採用
- 30年後:サイディング交換時期にDIYで焼杉板を施工
サイディングを張った後に焼杉板を張る工法なら、いっそのことサイディングの張替えの時期(20~30年後とか)に上から焼杉板を張った方がコストパフォーマンスとして良いんじゃないかという話になり、結局わが家は最初は焼杉板風のサイディングにして、交換の時期にサイディングの上からDIYで焼杉板を張ることにしました。
この方法により、初期費用を大幅に削減しつつ、将来的に本物の焼杉板外壁を実現する計画です。
省令準耐火でも安くで焼杉板外壁に出来る方法もあるっぽい。。。
調べてみると、15万円程度の追加費用で省令準耐火構造の要件をクリアしながら焼杉板外壁を実現する方法があることが分かりました。(たぶん)
具体的な方法:
• 構造用合板を「ダイライトMS」や「モイスTM」などの防火性能付き構造用耐力面材に変更
• 室内側に規定厚の石膏ボードを追加施工
参考にしたのが少し前の記事なので、今では15万より高くなってるかもしれませんね。
焼杉板外壁の実際のデメリット|岡山在住者の生の声
岡山県内で多くの焼杉板住宅を見てきた経験から、リアルなデメリットをお伝えします。
材料・施工方法による劣化の違い
焼杉板のメリットの1つでもある経年変化ですが、使う材料や設置場所によっては早い段階から激しく劣化します。
実際の例としては近所で施工したバーナー焼の焼杉板を採用したお家は、ものの1年で炭化層がはがれていました。
下の画像は築3~4年のバーナー焼の焼杉板外壁のお家ですが、炭化層はもはや無いに等しいです。
写真の左側は北側の外壁ですが、北側ですら剥がれてきてしまっています。
バーナー焼きは絶対に採用しない方が良いです!


バーナー焼ではない焼杉板外壁を採用した知り合いの家は軒があって雨が外壁には直接当たらない状況ですが、強烈な西日が当たる西面は炭化層がかなり剝がれていました。
焼杉板の外壁はノーメンテナンスを謡っているとはいえ、設置環境によっては注意が必要です。
物理的な損傷への脆弱性
ちょっと硬めのボールが当たろうものなら見事にボールの形にへこみます。
また通学路など、こどもが良く通る道に面していると、こどもにイタズラされることもあるようです。
ご近所さんは黒のマッキーで補修しているみたいです。。。
当然ながら汚れる
炭なのでいつまで経っても汚れます。触ったら黒くなります。
わが家の親族の築50年以上の家の焼杉板は触ってもあまり汚れませんでしたが、それはもう炭化層がかなり剥がれているからなんでしょうね。
逆に汚れるってことは焼杉板が外壁としてちゃんと仕事している証なのかもしれません。
わが家が採用した焼杉板風サイディングのレビュー
わが家はケイミューの焼杉板風の窯業サイディングを採用しました。


縦張りだとなぜか30万ほど増額。。。
縦張りだと水切りも入って意匠性が落ちるので、泣く泣く縦張りは諦めました。
焼杉板風の窯業サイディングでも見た目的には十分カッコいいのですが
押え縁が無いぶん立体感に欠ける
コーキングは少し気になる
コーナーの部材が窯業サイディング感を出してる
本物の焼杉板と比べると黒さが足りていない
このあたりがリアルな感想です。
黒い外壁は暑い?
熱伝導率が低い焼杉板なら黒の外壁でも問題はなかったのでしょうが、わが家は窯業系サイディング。
第3種換気のルフロを採用したわが家は、24時間換気の給気を通気層から取っています。夏場なら通気層内の温度は外気温以上に上昇しますが、黒の外壁ならなおさら。。。
軒が深く西日が当たりにくい立地なので、通気層内の温度がそこまで上がらないことに期待していますが、はたしてどうなるか。
入居して夏を越したらレビューしてみようと思います。
追記:夏を越したのでレビューしてみました!3種換気の給気口からの温度とかをまとめてます。
まとめ:焼杉板外壁を検討する際のポイント
それでは以上のことを踏まえてまとめです。
焼杉板外壁がおすすめな人
• 長期的なコスパを重視する方
• 独特の風合いと経年変化を楽しめる方
• 初期投資に余裕がある方
注意すべきポイント
• 省令準耐火構造での追加コストを事前確認
• バーナー焼きは避ける(三角焼きを選択)
• 設置環境(軒の有無、日当たり等)を考慮
• 物理的損傷への対策を検討
代替案の検討
• 焼杉板風サイディングでの当面の対応
• 将来的なDIY施工での本格導入
• 他の自然素材外壁(そとん壁)との比較検討
我が家はそとん壁も気になってたんですが、同じくイニシャルコストが高かったですね。
そとん壁はDIYで補修が出来ないのと、歴史が浅くて本当にノーメンテでいけるのかが不確定だったので、焼杉板に舵を切りました。
というわけで、今回は焼杉板について語ってみました。
デメリットはあるけれど、メリットと圧倒的な意匠性があるので、イニシャルコストは掛けてもいいよって人はぜひ検討してみてください!